6年秋〜冬になると、
「過去問って結局何年やればいいの?」
「宿題もたくさんあるのにどう進めればいいの?」
という悩みが必ず出てきます。
結論を言うと、
“何年分やるか”は志望校・お子さんの状況・家庭のペースによって違う けれど、
“基本の目安” と “バランスの取り方” を知っておくと、迷いなく進められるようになります。
この記事では、
●志望校別の適切な過去問年数
●繰り返し方
●宿題とのバランス
●先生への相談ポイント
をまとめました。
結論|過去問は何年分やる?基本の目安
第1志望校(本命)
5〜7年分が標準
学校によっては 10年分 やる家庭もある。
理由:
- 出題形式と相性が分かる
- 回数をこなすほど“その学校のクセ”が見えてくる
- 記述の質が安定する
第2志望校(押さえ校)
3〜5年分程度 がちょうどよい。
理由:
- 形式の把握が短時間でできる
- 直近3年を2周できると安心感が大きい
併願校(2/1午後校・2/2など)
1〜3年分で十分。
午後の学校は形式が安定していることが多いので、
直近2年を重点的に やるのが効果的。
志望校別の“必要年数”は変わる
難関校ほど、
“問題構造そのものへの慣れ” が必要だから年数が増える。
最難関・難関校(桜蔭・渋渋・早稲田・明明など)
最低5年、できれば7年以上。
特に算数は“学校ごとのクセ”を掴むのが必須。
中堅校(農大一中・成城学園・田園調布学園など)
3〜5年でちょうどよい。
2周目で得点が安定することが多い。
併願校(2/1午後・2/2共学など)
1〜2年+直近年度の解き直し が現実的。
過去問の“正しい繰り返し方”
① 直近3年は2周するのが基本
1周目:時間を測って、実力チェック(実際の試験時間と休憩時間を再現して4教科いっきにできるとベストできないときは1教科ずつでもOK)
2周目:弱点単元を拾う
3周目(余裕があれば):記述の精度を高める
② 古い年度は“傾向チェック”として見るだけでもOK
古すぎる年度(10年以上前)は
「今と大きく傾向が違う」こともあるので、
時間を測るのは直近年度に限定 してよい。
③ 問題全部やらなくてもいい(重要!)
- 得意科目は半分だけやる
- 明らかに出ない単元は飛ばす
- 記述は“型”を守れていればOK
家庭によっては「国語は過去問多め、算数は少なめ」など
科目バランスを変えても問題なし。
過去問と塾の宿題、どちらを優先する?正しいバランスの考え方
① 冬〜直前期は、基本は“過去問優先”でOK
ただしこれはあくまで 一般論。
お子さんの性格や弱点状況で変わることも多いです。
② 宿題は“全部消化”ではなく“優先度を絞る”だけで十分
例:
- 算数:計算・一行問題
- 国語:語彙・漢字
- 理社:受験校の頻出単元
→ これだけでも十分。
③ 宿題が重い日は“翌日にスライド”でOK
「今日宿題終わってない」がストレスになる家庭が多いけれど、
冬は 過去問の質>宿題の量 です。
④ 迷ったら、塾の先生に相談してOK(ここ大事)
- 今の時期は過去問と宿題どちらを優先すべき?
- 宿題はどこまでやるべき?
- 過去問は何年必要?
などは、先生がその子の状況を一番よく見てるので
遠慮なく相談して大丈夫。
相談すると
「宿題ここまでで大丈夫ですよ」
「志望校対策を優先していいですよ」
など具体的なアドバイスが得られることも多い。
⑤ 家庭で“優先ルール”を決めると迷いが減る
- 月水金は過去問
- 火木は宿題の基礎部分だけ
- 土曜は授業
- 日曜は直し・復習
など、
家庭で一度ルールを決めると親子で混乱しない。
まとめ|過去問は“年数より運用”が大事
- 第1志望は5〜7年
- 第2志望は3〜5年
- 併願校は1〜3年
- 直近3年を重点的に
- 宿題は必要な部分だけでOK
- 迷ったら先生に相談
- 家庭のルールを決めて回す
過去問は“量をやること”が目的ではなく、
その学校に慣れ、自分の弱点をつぶすためのツール。
焦らず、家庭に合ったペースで進めていきましょう。

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-1.jpg)
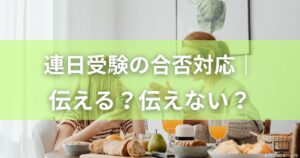
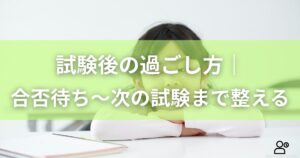

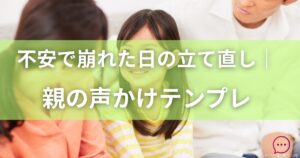
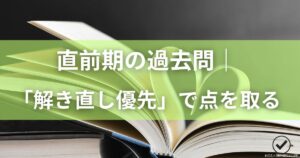

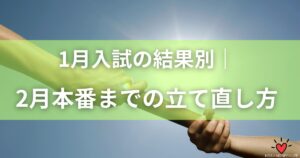
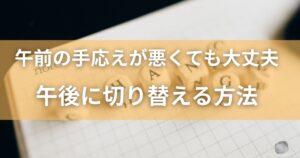
コメント