過去問を解き始めると、
「とりあえず解いたけど、直しをどうしたらいいかわからない」
「2周目って全部やるの?部分だけ?」
こんな悩みが必ず出てきます。
結論を言うと、
過去問は“解き直しの質”で伸びる科目です。
ただ解くだけでは点数は安定しません。
この記事では、
2周目・3周目で伸びる子が実際にやっている“正しい解き直しのやり方”
をまとめました。
まず大前提|過去問は「解いた回数」より“直しの質”が勝負
- 1周目の点数はブレる
- 得点に関係ない問題に時間をかけると逆効果
- 「なんとなく解く」を繰り返すと伸びない
→ 過去問は“直すところを選ぶ”ことが最重要。
解き直しの基本ステップ(全科目共通)
① まず間違えた問題を3種類に分類する
過去問はこの3分割が効率最強。
- A:ケアレスミス(本当は解ける)
- B:解法は知っているけど、処理が足りない・時間配分ミス
- C:本当に知らない・理解不足の単元
👉 解き直しの優先順位
A > B > C
Cを深追いすると、時間だけ奪われて壊滅しがち。
A・Bを潰すほうが点が一気に上がる。
② とくに算数は“間違え直し”が点数に直結
算数は以下の3つだけで急伸びする。
- 計算ミス(A)
- 基本問題の処理速度(B)
- 時間配分(B)
難問(C)を捨てたほうが得点は安定するのが真実。
③ 国語は「なぜその答えになるか」を言語化するだけでOK
記述は
- どの表現を拾うか
- 根拠の場所
- 説明の型
これだけ整理すれば十分。
点数の上下は気にしない(採点ブレが大きいから)。
④ 理科・社会は“単元を埋める作業”が9割
理社は
- 抜けている単元
- 苦手なパターン
- 語句・知識の漏れ
を埋めるだけで安定する。
2周目(2回目)のやり方|必ず伸びるやり方はこれ
① 時間は測らない(重要)
2周目は質の確認だけ。
時間を測るのは1周目と直近3年だけでOK。
② 全部やらず、間違えた問題だけでよい
算数なら:
- 大問全体を解くのではなく“落とした小問だけ”でOK
国語なら:
- 記述の部分だけ
- 選択問題の根拠確認だけ
理社なら:
- 間違えた単元だけ
③ 必ず「どう直すか」だけ言語化する
例)
- 計算は筆算を書く
- 図形は図の書き方を統一
- 語彙はノートに写す
- 理科は公式を1回書く
この“1行の言語化”が伸びる子の共通点。
3周目(最終チェック)のやり方|完璧にする必要なし
① 直近3年だけで十分
古い年度の3周目は不要。
時間も体力も奪われる。
② 間違えた問題の“最小限”だけ解く
- 算数:1周目 → 間違い直し → 3周目で“最後に落とした部分だけ”
- 国語:記述の型が整っていればOK
- 理社:頻出単元だけでOK
③ 1周目との差分を見る(点数は重要じゃない)
「何点取れたか」ではなく
**“どのミスが減ったか”**を見る。
解き直しが伸びる子の共通点(行動習慣)
- ミスの種類を分けている
- 書き方が一定
- 解法の“型”を意識している
- 過去問ノートをつけている
- 直しに感情を入れすぎない
- 本人が“変化に気づける”状態
このあたりは親のフォローが大きく効く部分。
過去問ノートの作り方(シンプルでOK)
① ページ左:問題番号+間違えた理由(A/B/C分類)
② ページ右:どう直す?(1行で書く)
例:
- 図を最初に書く
- “〜だから”で説明を書く
- 語句の漢字を覚え直す
毎日2〜3問でも続けると
直前期に爆伸びするノート になる。
まとめ|過去問は“直しの質”で決まる
- 1周目:現状把握
- 2周目:間違えた問題だけ
- 3周目:最小限の確認
- 点数より“どこが改善したか”を見る
- 難問を捨てる勇気が大事
過去問は、
ただ解くだけでは意味がない。
直しの精度で合否が変わる。
過去問や普段の宿題などどんな勉強でも、やり方は違えど、解き直しが一番大事だと感じています。
できない問題をみつける→できない問題の理由とできないものをできるようにする→もう一度解き直す。
ここまでで、初めて終わったよと言えるんだよとと娘には何度も何度も、しつこくしつこく、伝えてきました。
家庭でできるところだけ押さえて、
効率よく進めて合格にちかづいていきましょう!

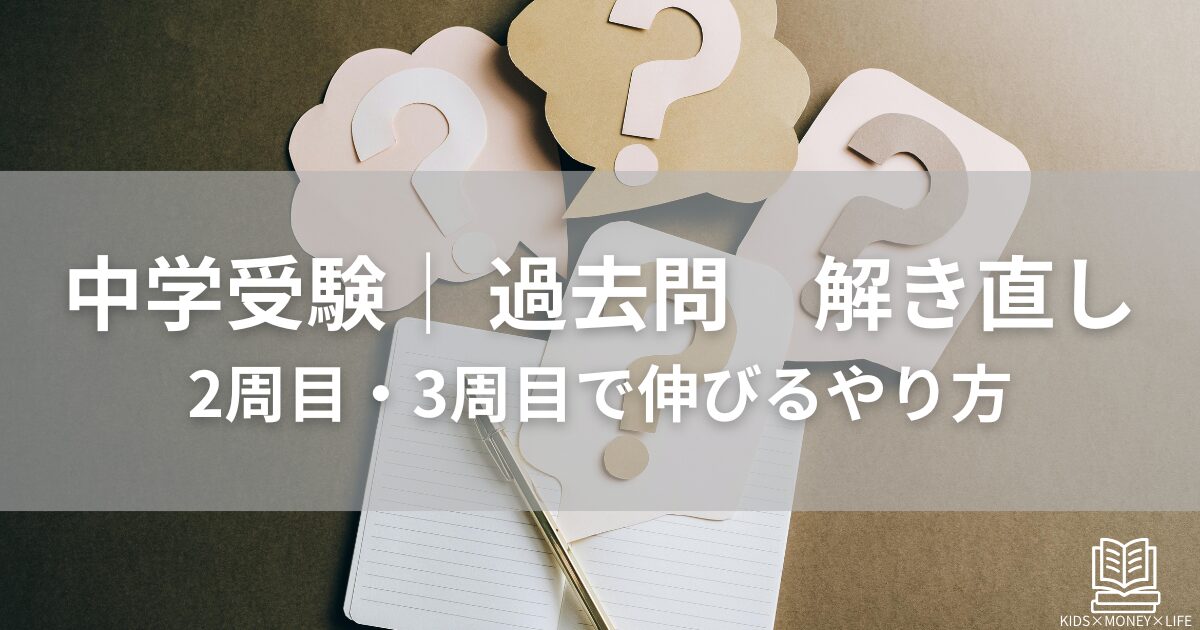
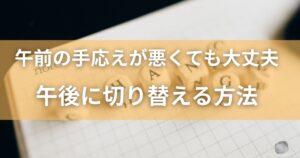







コメント