6年の冬——。
中学受験でもっとも伸びる子と、停滞してしまう子の差が最も大きく開く季節です。
理由はシンプル。
冬にやるべきことは「新しいこと」ではなく「今ある力を安定させること」だから。
そして2026年はサンデーショックの影響で、本番スケジュールもぎゅっと詰まる年。
だからこそ、冬の過ごし方が“本番での得点力”に直結します。
この記事では、11〜1月のやるべきことを
ママがすぐ実践できる形で、わかりやすく・ムダなく まとめました。
6年冬の全体戦略|深追いせず“安定化”が最優先
冬に伸びる子は、例外なく やることを絞っています。
逆に冬に崩れる子は、
- 苦手に過度に立ち向かう
- 夜遅くまで勉強を詰め込む
- 新しい問題集に手を出す
という“沼”にハマりがち。
冬の正解は 「量より質」「深掘りより安定化」。
① 過去問は“得意校を安定化”させる
過去問は「解ける→安定して取れる」状態に持っていくのが目標。
毎回同じ問題でブレるのは危険サイン。
② 苦手つぶしは“2〜3単元にしぼる”
冬に広げると破綻します。
算数なら「割合」「速さ」など、優先度の高い2〜3本に限定。
③ 算国の質を底上げ
得点源はこの2科目。
冬は算国の精度が合否の分かれ目。
④ 理社は“短時間×毎日”で記憶をキープ
冬に理社を重くすると崩れます。
30〜40分×2セットを淡々と。
11月〜1月の月別やること
11月|過去問の型をつかむ
- 5年内容の取りこぼし拾い
- 算数の“時間配分”と“取れる問題を落とさない”練習
- 苦手単元の絞り込み
→ この月で冬の戦略が決まる
12月|仕上げ期(量→質へ)
- 過去問は週2〜3回程度
- 難問より“確実に取る問題”を固める
- 冬休みで生活リズムを整え直す
→ 一番伸びる子が多い月
1月|得点力の維持とメンタル安定
- 新しいことは基本やらない
- 朝型リズムの最終調整
- 学校別の直前対策にしぼる
→ 最後に崩れない子=勝てる子
平日の勉強スケジュール(目安)
学校+塾という日は、子どもも親も“疲れている”。
だから短く・密度を高くが鉄則。
- 塾の宿題:60〜90分
- 復習:30分
- 過去問(軽めの1科目 ):30分~40分+直し60分
- 暗記:朝に回す(夜にやると忘れやすい)
夜に重い勉強を置くと翌日の疲労が抜けない。
冬は体調管理=得点管理。
休日の勉強スケジュール(目安)
休日は“やりすぎない”ことがポイント。
- 過去問:2科目 できるときは実際の試験と同じように4教科続けてやってみる。
- 直しはその日に全部やらない(翌日に回す)
- 理社:30〜45分×数セット
- 午後は軽めの復習+自由時間少し
- 夕方は休ませる
親が日曜に張り切りすぎると、月曜に崩れる家庭が多いです。
ただ、我が家の場合日曜日はほぼ模試or日曜ゼミの塾の授業で埋まっていました。
女子の冬勉強で気をつけること
女の子は冬に“気温・体調・精神状態”の影響が勉強に直結します。
- 冷えると集中が落ちる
- 生理周期が乱れやすい
- 睡眠不足=点数ダウン
- 夜の暗記が頭に残りにくい
- 夜に泣きやすい時期がある
女子は冬が一番やさしく、丁寧に支えてほしい季節。
冬に“やらないほうがいい”こと
冬に伸びない子の共通点がこちら:
- 新しい問題集を買い足す
- 間違いノートを作りこみすぎる
- 毎日、長時間過去問
- 点数に一喜一憂する
- 夜更かし勉強
どれも負荷が大きく、伸びるタイミングを逃します。
まとめ|6年冬は“深掘りより安定化”で合格に寄せる
- 新しいことを増やさない
- 得点源の安定化が最優先
- 過去問は“取れる問題の確実化”
- 理社は短く毎日
- 夜は軽く、朝に回す
冬に崩れない子=本番で勝てる子。
今まで頑張ってきたことを信じて実力を出せるように訓練する時期。
この2、3か月で、びっくりするほど伸びる場合もあるので注視して大事に一日一日すごしていきたいと思います。
合格を勝ち取りに行きましょう!

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピーのコピー.jpg)
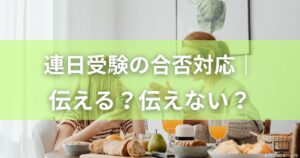
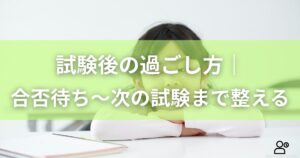

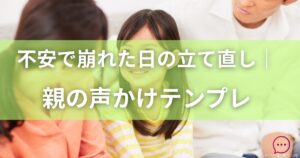
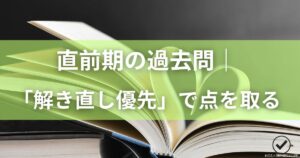

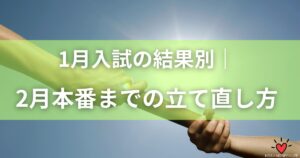
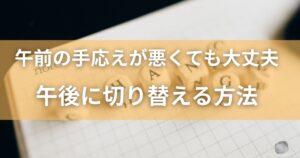
コメント