11月に入ると、いよいよ受験シーズンが現実味を帯びてきます。
でも、焦る気持ちのまま冬期講習に突入してしまうと、
「何をやっても身につかない」「ただこなすだけ」になりがち。
だからこそ今は、一度立ち止まって整えるタイミング。
各教科の“リセット”をしておくと、冬期講習がまるで違います。
今回は母ちゃん目線でまとめた、家庭でできる「教科別リセットチェックリスト」を紹介します。
🟥 国語|読み方の“型”を整える
国語は「センス」じゃなく「型」で伸びます。
冬前に、読み方や解き方のクセを一度リセットしておきましょう。
✅ チェックリスト
- 設問を先に読む癖がついている
- 指示語・接続語の意味を意識して読めている
- 記述問題で「抜き出し+自分の言葉」を意識している
📒 家でできること
- 模試の長文を再利用して「読解しなおし」
- 音読を1日5分(声に出すだけで理解力アップ)
- 「この文の主張って何?」と話してみる
💬母ちゃんメモ:
正解よりも、「読む筋力」を育てる時期。
いっしょに読み返して「ここ、前よりスッとわかったね」と声をかけてみよう。
🟦 算数|スピードより“思考の道筋”をリセット
焦ると「早く解けるか」に目が行きがちだけど、
冬前はあえてゆっくり・丁寧に考える練習を。
✅ チェックリスト
- 途中式を省略していない
- 答えだけ出して「説明できない」状態になっていない
- ケアレスミスの原因を言葉で説明できる
📒 家でできること
- 苦手単元を3つだけピックアップして「考え方ノート」を作る
- 問題を解いたら「どうしてそう考えたか」を口に出す
- ミス問題を3問だけ解き直す(“少なく深く”がコツ)
💬母ちゃんメモ:
スピードより「筋道」を思い出す時間。
冬期講習では難問演習が増えるから、今のうちに“解く土台”を固めよう。
🟩 理科|知識より“つながり”を整理
理科は覚える量が多いぶん、点が伸びにくいと感じやすい教科。
でも、「なぜそうなるか」を理解できると一気に安定します。
✅ チェックリスト
- 計算系(浮力・濃度・電流など)があいまい
- 実験問題の手順を説明できない
- 似た現象を混同している(例:蒸発と沸騰など)
📒 家でできること
- 苦手単元を口頭テスト形式で出し合う
- ノートを見ながら「これは何と関係してる?」と聞いてみる
- 理科辞典や図鑑を使って“調べ直す時間”をとる
💬母ちゃんメモ:
覚えるだけの理科から、“つながって見える理科”に。
「なぜ?」を一緒に考える時間が、冬の伸びをつくる。
🟨 社会|“暗記リズム”を立て直す
社会はどうしても後回しになりがち。
でも、今ここでリズムを整えると、冬以降の伸びがまるで違います。
✅ チェックリスト
- 「地理だけ」「歴史だけ」に偏っている
- 一問一答で覚えて終わっている
- 苦手分野を避けて復習していない
📒 家でできること
- 朝5分だけ「社会タイム」を作る(食卓でOK)
- 覚えたことをクイズにして出し合う
- “漢字で書けない用語”を洗い出しておく
💬母ちゃんメモ:
暗記は「根性」より「テンポ」。
コツコツより“サラッと続ける”ほうが、案外残る。
まとめ|“整える時間”が冬の伸びを決める
冬期講習は「量の勝負」になりがちだけど、
ほんとうに伸びる子は、始まる前に頭と心を軽くしておく子です。
焦らず、ゆるやかに、整える。
このひと手間が、冬の成果を何倍にもしてくれます。
📣 次回予告:
「冬期講習を“消化で終わらせない”ための家庭フォロー法」

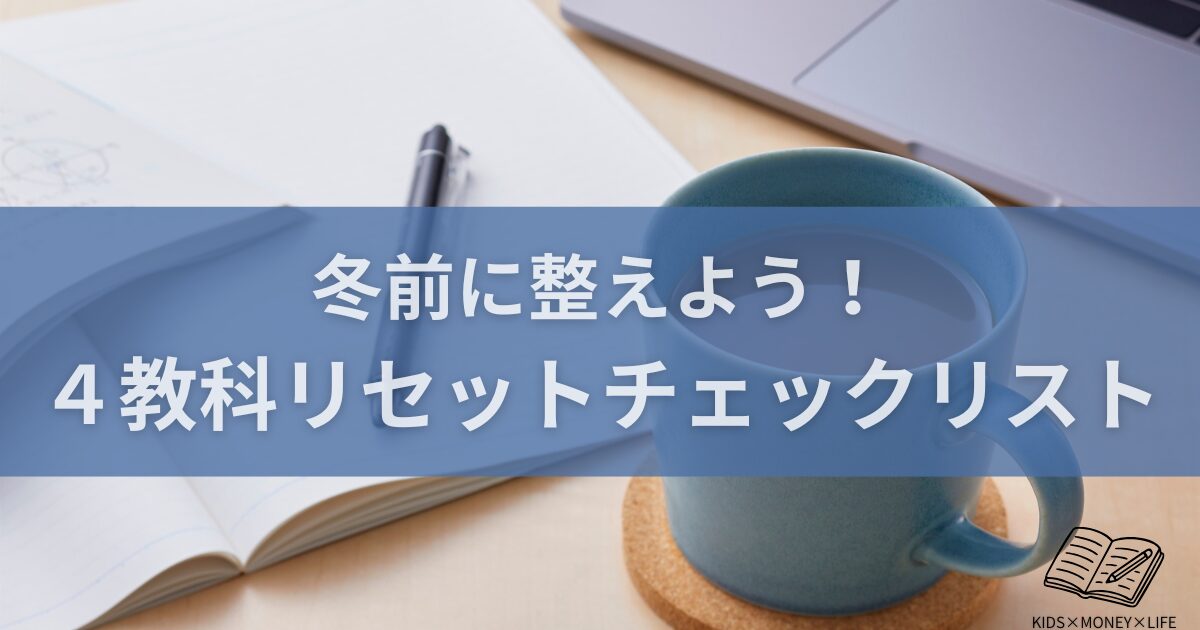
-300x158.jpg)
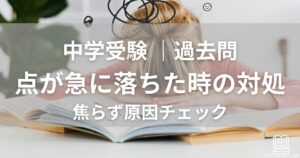
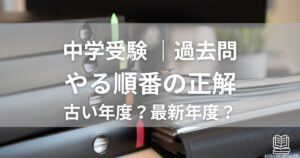
-300x158.jpg)
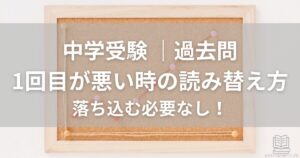
-300x158.jpg)
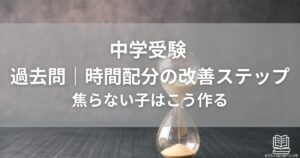
-300x158.png)
コメント